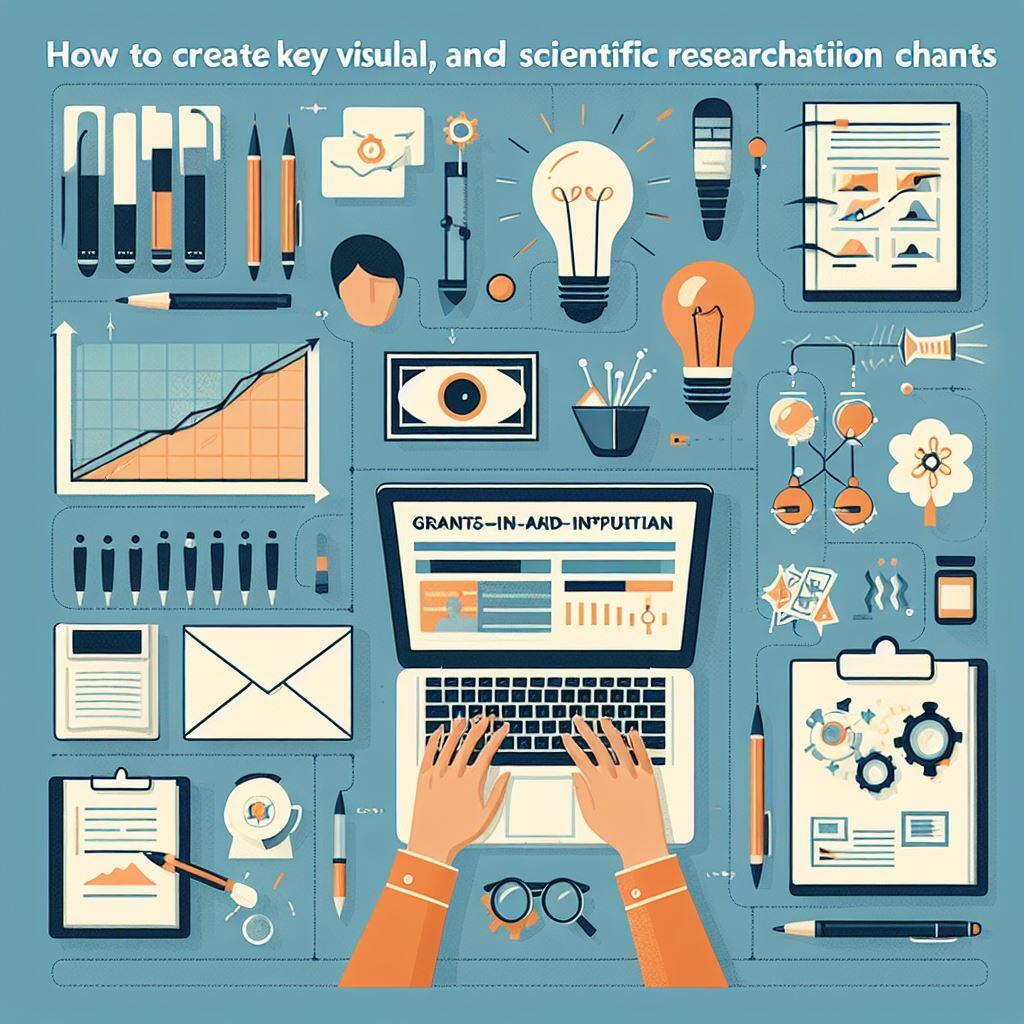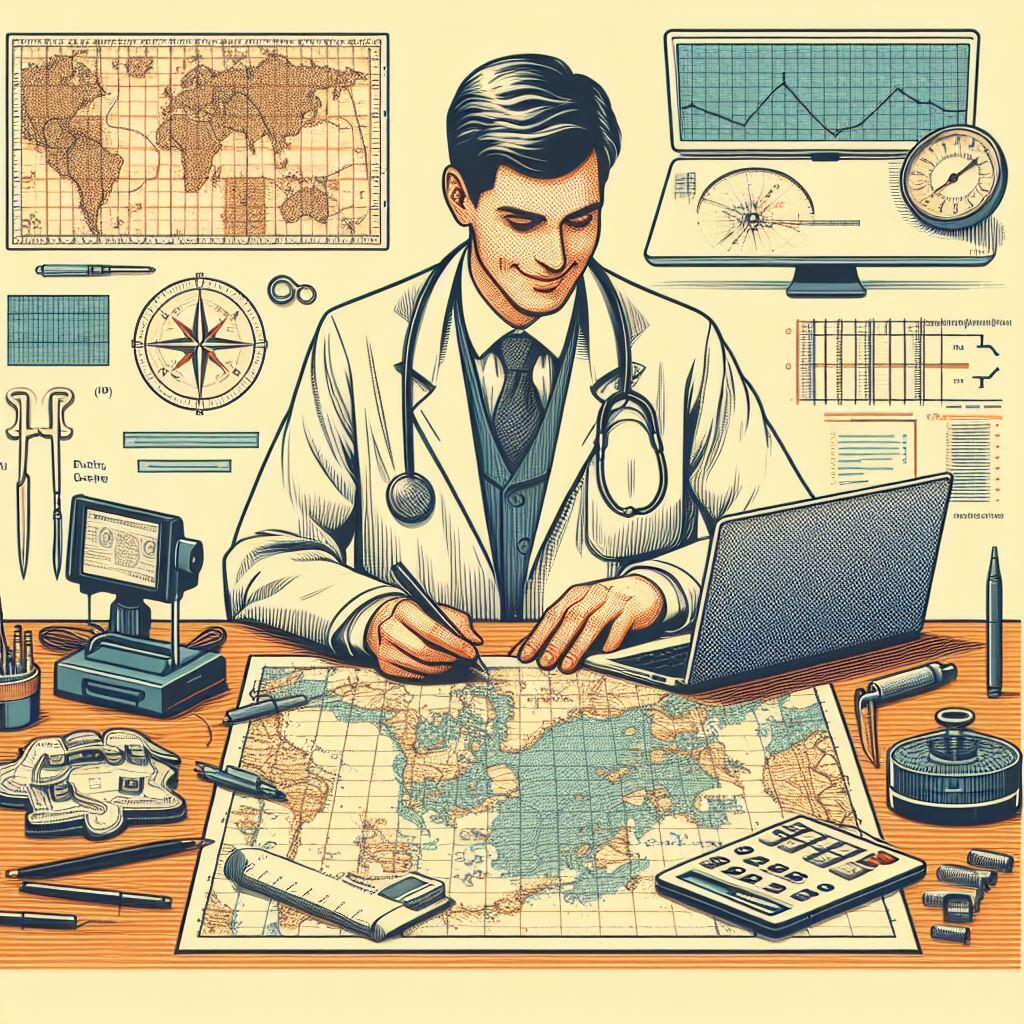本コラム内で触れている生成AIの活用例は、あくまで一般構造の確認に限定したものです。当社では、 ISO27001取得にあたり、社内ルールとして、研究内容の機密性・申請書の未公開情報についてはAIに直接入力・共有しないことを徹底しています。また、汎用的な構造要素(例:SCOAP分析)に関しても、ローカル環境または管理された安全なAI環境での利用を基本とし、情報が第三者の学習データや共有情報に含まれることがないよう配慮しています。
お客様に、「ここまで画像生成AIが進むと、もう仕事なくなるんじゃありませんか?」とご心配いただくことがある。
その方は、ありがたいことに、当社のサービスを何度もご利用くださっている。
だが、お話を伺っていると、なぜご自身がリピートしているのか、その本質にはまだ気づかれていないようにも感じる。
■ 生成AIの進歩は、すでに“代替可能領域”を変えつつある
確かに、生成AIによって、いわゆる「メディカルイラストレーション」と呼ばれる領域の一部が、すでに代替可能になっているのは事実だ。
だが、それは私たちが取り組んでいるアカデミック・メディカル・イラストレーション(“論文や研究発表に特化したビジュアル設計”)とは異なる次元の話である。
たとえば――
- 一般的なインフォグラフィックやヘルスケア系のアイコン
- 細胞や臓器などの定型化されたパーツ
- オミクス系の教科書的構造図 など
これらは、集合知に近い標準化された視覚言語であり、AIによって効率的に再生成できる。
かつて時間をかけて描いてきた素材が、数秒で再現されるのを見ると、職能としての危機感すら覚える。だが、そもそもそれらは、「誰のものでもない知」で構成されているものであり、オリジナリティを語れる類のものではない。
AIに置き換わっても、当然の成り行きだとすら思う。
なお、以下は、あくまでアカデミック・メディカル・イラストレーションの文脈であることにご留意願いたい。
■ ゼロから“それっぽい”案を出すのは大得意(しかし・・・)
AIの真骨頂は、何もない状態からの「案出し」や「多様なスタイル生成」だ。
構図案、色のトーン、初期スケッチ。こういったものは、AIのスピードと網羅性に助けられる。
当社でも実際に、コーディネーター職が初期ラフやアイデア収集の段階でAIをツールとして併用するケースは増えている。
しかし、そのままでは“伝わる表現”にはならない。
研究の背景や目的、読者の理解度、審査基準といった文脈を踏まえたうえで、「この研究をこの図で、なぜこう見せるのか」を説明可能な状態に落とし込む必要がある。
■ 具体的な文脈・目的を与えようとした瞬間、AIは破綻する
「わかりやすい図」を描くことは結果であり、私たちの業務の本質ではない。
「この研究が、誰に、なぜ、どう伝わるべきか」を読み解き、可視化することにある。
MEDICAL FIG.では、医学的正確性・対象者の理解度・使途(学会か論文か教育か)によって、図の構成、描写レベル、訴求の角度を設計し直す。
GrantVにおいては、研究計画の意義・構成・審査委員の視点に立った“戦略的な見せ方”を設計する。
こうした仕事は、生成AIが苦手とする「個別最適化」「文脈理解」「評価者心理の把握」に支えられている。
つまり、3,000人以上の医師や研究者の「まだまとまりきらない想い」と向き合ってきた経験値こそが、当社が提供している価値であり、それゆえに、お客様がリピートしてくださる理由でもある。
■ なぜ“脳内トレース”はAIに任せられないのか
仮に、研究者自身が「こんな図がほしい」と思った瞬間に、生成AIにスクリプトを投げて完全な出力が得られるような時代が来たら──それは確かに便利だろう。
だが、その未来は、少なくとも当面は訪れない。
なぜなら、研究者の“頭の中”は、単なる情報ではなく、経験・文脈・評価軸・伝えたい相手の視点が織り込まれた「意図のかたまり」だからだ。
それを図にするには、“情報を翻訳する存在”=私たちのような可視化の専門家が必要になる。
ましてや、論文の査読者しかり科研費申請書の審査委員しかり、彼らの”頭の中”も相応に複雑である。
■ ニッチであることは、むしろ強みになる
サイエンスイラストレーターの大内田美沙紀さんの記事に、AI研究者の川村秀憲先生の言葉が引かれていた。
ニッチな技術や独特の感性など,わずかな人にしかできないことは,技術的にAIで代替できる可能性があってもそれを開発する経済的合理性は低い。
アカデミック・メディカル・イラストレーション、医学論文や研究計画書に特化したビジュアル化の仕事は、まさにその典型である。
- 医学 × 表現
- 研究構想 × デザイン
- 審査戦略 × 視覚化
こうした“掛け合わせ型の翻訳技術”はテンプレート化されにくく、だからこそAIの隣で並走しながら、独自の価値を発揮できる。
■ AIに疲れてしまったら、それは“構造の整理”に疲れているのかもしれない
生成AIを使ってみたものの、なんとなく進まない、疲れてしまう。
それは、AIの性能の問題というより、自身の問いの構造がまだ整理されていないからだ。
つまり、“何を聞けばいいのかがわからない”時点で、AIは壁打ち相手にはならないのだ。
いや、自分が聞きたいことくらい分かっている、そう思っている方は、自分がAIにお疲れの理由をお分かりではないのだろう。
そもそも研究論文や科研費申請書で使用するビジュアル要素は、「問いの構造」そのものが複雑なのだが、研究者自身が自身の高コンテクスト性に気づいていないことも多いから厄介である。
私たちは、本人が整理されていると思っている情報についても、少なくとも「分からないことは分かりません」というし、「伝わらないものは伝わりません」という。
そうした整理されていない研究の素材やアイデアに向き合い、「どう見せれば、誰に伝わるのか」を一緒に再構成していく。
■ なぜ、当社をリピートしてくださるのか
冒頭に戻ろう。
なぜ、そのお客様は、毎回当社に依頼をしてくださるのか。
それは、AIでは“研究の伝達”が完結しないことを、肌感覚で理解されているからだ。
研究者であるお客様ご自身は、まさに専門職のど真ん中にいる。
だが、その研究成果を他者に「正しく、魅力的に、戦略的に」伝えることは、また別の専門性を必要とする。
高度に専門的な領域においては、まだまだ生成AIには難しいことだということを無意識に自覚されているのだろう。
そこに私たちのような、ビジュアル化の専門家=“情報の翻訳者”の役割があるのだなと実感する。
何度もご依頼くださる方々は、単に「絵がうまいから」ではなく、
まだ整っていない段階でも相談できるという点に価値を感じてくださっているように思う。
私たちは、AIとまったく競わない。
アカデミック・メディカル・イラストレーションの領域において、 「どこまでをAIに任せ、どこからを人間が引き継ぐか」を明確に線引きすること。
これこそが、生成AI時代における専門支援者の生存戦略だと思っている。
今後も、AIと人間が補完し合う関係性を構築していきつつ、ニッチなこの領域で爪を研いでいく。